塾業界は終わり?その背景と今後を徹底検証

この記事の監修者

教育転職ドットコム 田中
代表取締役
詳しく見る教員の道を志すもまずはビジネス経験を積もうとコンサルティングファームに入社の後、リクルートに転職。人事採用領域と教育領域で12年間、法人営業および営業責任者として従事し、年間最優秀マネジャーとして表彰。退職後、海外教育ベンチャーの取締役などを経て株式会社コトブックを創業。大手学習塾や私立大学など教育系企業のコンサルティングなど教育領域に関する知見を活かし、教育領域の転職支援を行う傍ら、京都精華大学キャリア科目の非常勤講師も務める。
Q. 「塾業界は終わり」と言われるのは本当?
A. 完全に終わるわけではありません。
少子化・競合の多様化・大学入試の変化などにより、従来型の塾は厳しい局面に立たされています。現在は、勝ち残る塾と淘汰される塾が二極化している状態です。
近年「塾業界が終わる」との声がSNSやニュースでも見られるようになりました。
実際、塾の倒産件数が過去最多を記録するなど、逆風が吹いているのは事実です。しかしその一方で、成長を続ける学習塾も確実に存在しています。
塾業界が「終わる」と言われる背景・現状・そして成長を続ける塾の共通点から転職時に見るべきポイントまで、徹底的に解説!
塾業界を取り巻く環境
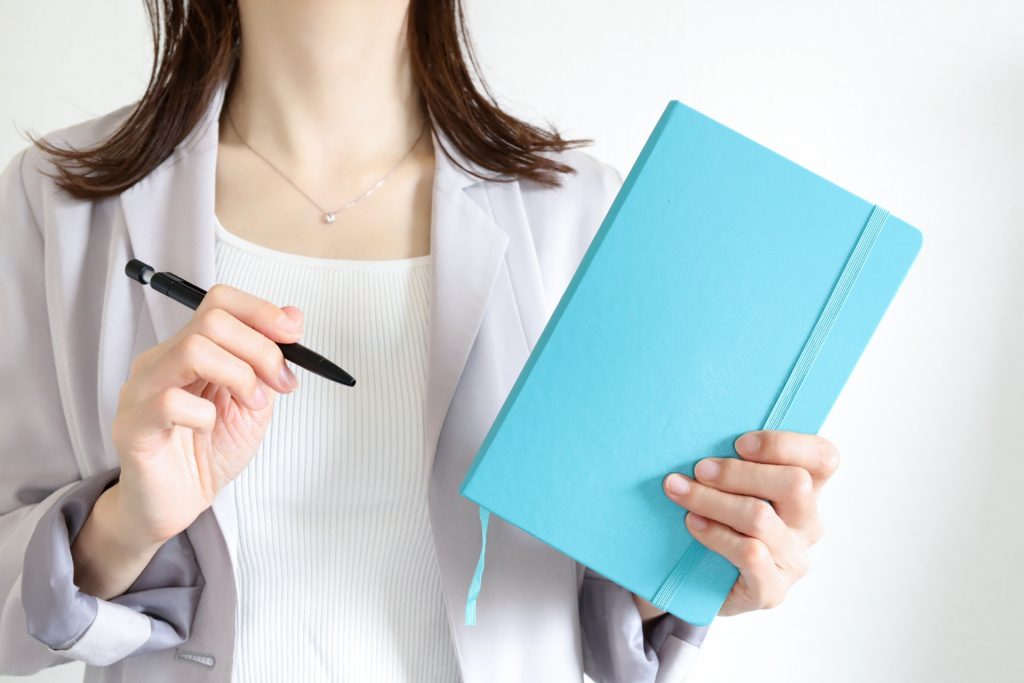
塾業界の経営が厳しいと言われる理由は?
塾業界を取り巻く急速な環境の変化により、塾業界の経営が過去と比べて難しくなってきていることは事実です。
- 少子化
- 大学進学難易度の変化
- オンライン学習サービスの台頭 など
塾業界の経営が厳しさを増している最大の要因は「少子化」です。子供の数が減り、塾同士の生徒獲得競争が激化しています。
また、オンライン学習サービスや無料学習コンテンツの台頭により、学習の選択肢が多様化しています。その結果従来の塾に通う必要性を感じない家庭も増えています。
さらに、学習指導要領の改訂によって求められる学力が変化。塾も新たな教育内容への対応を迫られています。
これらの変化に対応できない小規模な塾は倒産に追い込まれるケースも増え、塾業界はまさに変革期を迎えています。
少子化によって子供の数は減り続けている
「少子化」塾業界にとって、最も深刻な問題です。
日本の出生数は年々減少し、2023年には過去最低を記録。このままでは将来的に子ども全体の数が大幅に減少し、塾に通う生徒の母数が縮小します。
結果として、塾間の生徒獲得競争は激化することが予想されます。
そのため、生徒一人あたりの単価を引き上げるか、より多くの生徒を集めるための差別化が不可欠となります。
特に地方ではこの影響が顕著で、生徒が集まらず閉校に追い込まれる塾も少なくないことが想定されます。
大学進学がしやすくなっている
少子化に伴う影響として、一部の大学で入学が容易になることも考えれます。
その結果、「塾に行かなくても大学に行ける」と考える層が増え、塾の必要性を感じにくくなる可能性があります。
特に、学力向上を主眼とする進学塾は、顧客獲得が難しくなるかもしれません。
一方で、多様な入学方式に対応するため、総合型選抜や推薦入試対策を求める生徒は増えることが考えられます。
そのため、新たな指導ニーズが生まれます。しかし、これらの対策は個別指導の要素が強く、集団授業中心の塾にとってはビジネスモデルの転換が求められます。
オンライン学習サービスの台頭
近年、急速に存在感を増しているのが、オンライン学習サービスです。
場所や時間にとらわれずに学習できる手軽さ、安価な料金設定、AIを活用した個別最適化された学習などが魅力で、特に都市部以外の生徒や、部活動などで忙しい生徒に支持されています。
YouTubeなどの無料学習コンテンツも質の高いものが増え、基礎的な学習であれば無料で完結できる環境が整いつつあります。さらに、大手出版社やIT企業が提供する教育アプリや教材も学習の選択肢を広げています。
これらの多様な競合の台頭は、塾が提供する価値を再定義し、従来の「教室に通って授業を受ける」という形態だけではない、新たなサービスの提供を迫っています。
塾業界の現状

塾業界はM&A(合併・買収)も活発化。勝ち残る塾とそうでない塾の二極化が進んでいます。経営環境が厳しさを増す中で、生き残りをかけた再編が進む塾業界の現状と、その背景にある構造的な変化を解説します。
急速に進むM&A
塾業界のM&Aには、生き残り戦略としての多様な事例が見られます。
・大手塾による、地域密着型の中小塾の買収
・EdTech企業や異業種による塾事業の買収
生徒数確保のために、大手塾が中小塾を買収したり、新たな学習ニーズへの対応のため、シナジーのある異業種が塾事業を買収する動きも活発化しています。
大手学習塾「ベネッセホールディングス」や、「駿台グループ」も、オンライン学習を提供する会社をそれぞれ子会社化し、新たなサービス提供を始めています。
後継者不足に悩む中小塾が、事業承継を目的に大手傘下に入る事例も増加しており、M&Aは業界再編の大きな要因となっています。
出典:経済産業省 特定サービス産業動態統計調査 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabido/result-2.html
業績を伸ばす塾と、そうでない塾が二極化
塾業界の勝ち組は、戦略的なM&Aで規模を拡大し、生徒基盤を強化。
オンライン学習やAIを駆使した個別最適化学習で効率と質を高めています。
さらに、多様な入試形式やプログラミング教育など、入試ニーズの多角化に迅速に対応。質の高い講師と手厚いサポートでブランドを確立し、厳しい市場で優位に立っています。
一方、負け組は少子化やデジタル化の波に乗り切れず、生徒数減少や後継者問題に直面し、淘汰されつつあります。
二極化は、今後さらに加速するでしょう。
成長している塾業界のトレンド
- オンライン融合
- 中学受験や通信制高校への対応
- マーケティング戦略
- 戦略的な採用活動
トレンド➀オンライン融合
成長を続ける学習塾は、オンラインとオフラインをシームレスに融合したハイブリッド学習モデルを確立。
コロナ禍を経て、生徒や保護者の学習ニーズが劇的に変化したことを受け、単なるオンライン授業の導入に留まらず、オンライン・オフラインそれぞれのメリットを最大限に引き出す戦略を展開しています。
- オフライン:教師での質の高い対面指導
- オフライン:時間や場所を選ばない補修・個別質問対応
これにより、生徒は部活動や他の習い事と両立しやすくなり、新たな学習体験の機会が生まれています。
塾側も、オンライン活用で教室運営コストの削減や、講師の効率的な配置が可能となり、経営効率化に繋がっています。この柔軟かつ効率的なモデルが「勝ち組」の塾を支える大きな要因となっています。
トレンド➁多様化するニーズへの対応(中学受験、通信制高校)
成長する学習塾は、画一的な指導から脱却し、生徒や保護者の多様な学習ニーズへ柔軟に対応しています。特に顕著なのが、中学受験と通信制高校への需要増への対応です。生徒の学習を多角的に支えることで、新たな顧客層を確実に獲得しています。
| 中学受験対策 | ・知識だけでなく、思考力・記述力を問う入試傾向に対応 |
|---|---|
| 通信制高校受験対策 | ・レポート作成支援や単位取得、大学進学に向けた個別指導 ・学習面だけでなく「居場所」としての役割も担う |
中学受験対策では、従来の詰め込み型ではない、より本質的な学習を提供。各私立中学の多様な教育理念に合わせた個別対策も強化しています。
また、不登校や個性的な活動を行う生徒が増える中で、通信制高校の生徒へのサポートも拡充させています。
トレンド③マーケティング戦略
成長する学習塾は、生徒や保護者に価値を的確に伝えるマーケティング戦略も重視。競合が激化する中で「選ばれる塾」となるため、以下の点に注力しています。
| コンテンツマーケティング(webサイト/SNS) | データに基づきターゲット層を明確化オンライン広告で効率的なリーチ獲得塾の魅力や合格体験記を発信 |
|---|---|
| 口コミの活用 | 質の高い指導と手厚いサポートで生徒、保護者の満足度を高めて、ポジティブな口コミ評価を獲得 |
| 地域密着型マーケティング | 地域イベント参加や無料の体験会実施により、見込み客との直接的な接点を創出 |
これらの広報戦略を組み合わせることで、集客力を高め、持続的な成長を実現しています。
トレンド④人材獲得競争
優秀な人材の獲得も喫緊の課題となっています。成長を続ける塾は、この激しい人材獲得競争を勝ち抜くため、戦略的な採用活動を重視しています。
単に高待遇を謳うだけでなく、講師が「この塾で働き続けたい」と思える成長機会を提供。
- 講師から教室長、エリアマネージャーへの昇進、
- 教材開発などの専門職への道も用意
上記のような、多様なキャリアパスを描ける環境を整備しています。
これにより、講師のモチベーション向上と長期的な定着を促しています。
同時に、採用経路も進化。採用に特化したWebサイトやSNSで塾の理念、働く環境、社員の声を積極的に発信し、共感する人材を惹きつけています。
正しい戦略をもっている塾は勝てる市場
これまで見てきたように、少子化やオンライン学習の台頭で「終わり」と囁かれる塾業界。しかし、その実態は、戦略次第でまだまだ勝てる市場です。時代の変化を的確に捉え、実行できる塾こそが勝ち抜き、成長を続けています。
伸び続けている学習塾は複数存在
複数の学習塾が成長を続けているこの事実は、塾業界が戦略によって十分に勝てる市場であることを明確に示しています。
経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」によると、学習塾の売上高指数は2020年を除き増加傾向で推移。受講生一人あたりの売上高も2016年以降増加を続けています。学習塾全体においては、むしろ市場が拡大しており、戦略次第で大きな成長が遂げられるのです。
出典:経済産業省 https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20240321hitokoto.html
大手学習塾の戦略
大手学習塾は、激化する競争環境で勝ち抜くため、多角的な戦略を推進しています。
例えば大手教育サービス会社「トライグループ」は、オンライン家庭教師の導入やAIを活用した個別最適化指導など、DX(デジタルトランスフォーメーション)を積極的に推進し、学習の質と効率を高めています。大学入試改革への対応や、特定ニーズへのきめ細やかなサポートも特徴です。高品質な指導を支える人材育成と、長年の実績で培ったブランド力も強みとなります。
このような特徴に当てはまる大手学習塾は、変化を捉え、テクノロジーと多様なサービスで進化し続ける成功モデルと言えるでしょう。
出典:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC092C20Z01C21A0000000
塾業界で働く時に、見るべきポイント
塾業界への転職時に気にするべきポイント
- 直近の売上伸長率
- 今後の教室出店計画
- 競合優位性
- 人材への教育投資
直近の売上伸長率
塾業界への就職・転職を考える際、「直近の売上伸長率」は非常に重要な判断ポイントです。少子化や多様な学習ニーズの増加で業界全体が変革期を迎える中、売上を伸ばしている企業は、明確な成長戦略を持ち、変化に適応できている証拠だからです。
売上が伸びている塾は、オンライン融合や個別指導の強化、新しい教育プログラムの導入など、顧客ニーズを捉えたサービス展開ができている可能性が高いです。
このような企業は、今後も成長が見込まれるため、キャリアの安定性や自己成長の機会も期待できます。
求人情報や企業説明会では、直近の業績や成長戦略について積極的に確認し、自身のキャリアプランに合った企業を見極めることが重要です。
今後の教室出店計画
塾業界への就職・転職では、企業の今後の教室出店計画も重要です。単なる拡大ではなく、少子化の中で戦略的な出店をしているかが見極めるポイントとなります。
成長企業は以下を重視していることが多いです。
- 既存校舎の最適化やM&Aを組み合わせて拠点を拡大
- オンライン連携を前提とした小規模な特化型教室や、成長が見込める地域への出店
データに基づく効率的な投資で、生徒獲得や顧客ニーズへの対応力を高める計画を持つ企業は、将来性があると言えるでしょう。
競争優位性
塾業界で就職・転職する際、企業の競争優位性を見極めることは極めて重要です。少子化や多様な競合がひしめく中で、明確な強みを持つ塾こそが生き残り、成長します。
ハイブリッド学習、特定のニーズ(中学受験、通信制高校など)に特化した指導、データに基づく効果的なマーケティング、そして優秀な人材を惹きつける手厚い投資などの独自性は、他社との差別化隣、生徒と保護者から選ばれ続ける理由となります。
人材への教育投資
塾業界で就職・転職を検討する際、企業の人材への教育投資は極めて重要です。質の高い教育サービスは、最終的に優秀な講師やスタッフによって提供されるからです。
成長している塾は、採用後の研修制度を充実させ、指導力や専門性を継続的に高める機会を提供します。また、明確なキャリアパスを用意し、講師が将来を見据えて働ける環境を整備。こうした人材への手厚い投資は、社員の定着率を高め、結果として指導の質の向上と顧客満足に繋がります。
自身の成長と安定したキャリアを望むなら、この点に着目しましょう。
まとめ
学習塾業界は厳しくなるが企業によっては高い成長率を出していることが、以上の記事によって明確になったのではないでしょうか。
働く時にはしっかりと企業調査をし、ご自身に適した塾を見つけましょう。
この記事の監修者

教育転職ドットコム 田中
代表取締役
詳しく見る教員の道を志すもまずはビジネス経験を積もうとコンサルティングファームに入社の後、リクルートに転職。人事採用領域と教育領域で12年間、法人営業および営業責任者として従事し、年間最優秀マネジャーとして表彰。退職後、海外教育ベンチャーの取締役などを経て株式会社コトブックを創業。大手学習塾や私立大学など教育系企業のコンサルティングなど教育領域に関する知見を活かし、教育領域の転職支援を行う傍ら、京都精華大学キャリア科目の非常勤講師も務める。








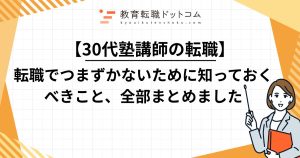
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 塾業界は終わり?その背景と今後を徹底検証 | 教育転職ドットコム […]